2024年3月1日
- 小学生
- 教育
- 子育て
- 学習方法
虫と昆虫はどう違う? 子どもにもわかるその違いを解説します
子どもに「虫と昆虫はどう違うの?」と聞かれたとき、正確に答えることができるでしょうか? 夏になると子どもと一緒に昆虫採集をする機会もあるでしょう。そんなとき、自信を持って答えられるよう、虫と昆虫の違いについての知識をご紹介します。
虫と昆虫の違い 昆虫には3つの明確な条件がある

普段、あまり意識しないで使っている「虫」という言葉について、その意味を見ていきましょう。
虫とは
虫とは、節足動物や爬虫類の一部、両生類の一部などを指す言葉です。
節足動物は、足が節に分かれている動物のことをいいます。また、小さいトカゲやイモリ、ミミズなども虫と呼ばれます。
昆虫以外の節足動物
クモ・ダニ・サソリなどは、足が節に分かれていますが昆虫ではありません。また、エビ・カニ・ヤドカリ・ダンゴムシなども節足動物ですが、昆虫ではなく甲殻類に分類されます。
昆虫の3つの条件
昆虫は節足動物なので虫の一種です。つまり、虫の中に昆虫も含まれるということです。
生き物を分類するときには、門-綱-目-科-種という順番に分けていきます。この中の「綱」に、「昆虫綱」として分類されているのが昆虫です。
昆虫には3つの条件があります。
1. 体が頭部、胸部、腹部の3つに分かれている。
2. 胸部に1対ずつ、3対の脚がある。
3. 羽が4枚ある(一部アリ・ハエなどの例外もある)。
虫には昆虫のような条件はない
クモやダンゴムシには脚がありますが、「胸部に1対ずつ、3対の脚がある」という昆虫の条件から外れているので、昆虫ではないということになります。ミミズも脚やその他の条件から外れています。
辞書を引くと、「昆虫網ではなく、人類・獣類・鳥類・魚介類以外の小動物は虫である」という説明がされています。
虫の定義はあいまい
虫という漢字は、へびの形から作られた象形文字といわれています。もともと虫は、毒を持ったへびを意味する言葉でした。また、ミドリムシやギョウチュウなど、虫ではない生き物にも虫を連想させる言葉が使われています。
昆虫には明確な条件がありますが、虫の定義はあいまいといえるでしょう。
昆虫のさまざまな特徴 「複眼」「触角」「変態」など

では、昆虫について、もう少し詳しく見ていきましょう。
「複眼」という特徴的な目を持つ
目の特徴として、たくさんの小さな目が集まってできた「複眼」を持っている昆虫がいます(複眼を持たない昆虫もいます)。複眼の場合は、視野が広くなり、動きのあるものを素早く捕らえることができます。敵から逃げるときや獲物を捕らえるときに役立つといわれています。
触角のさまざまな役割
多くの昆虫には頭に一対の触角があります(触角がない昆虫も一部います)。触角には、大きさ、硬さ、温度のほか、においや味を感じる役割もあります。また、体のバランスを保ったり、仲間とコミュニケーションをとったりする際にも、触角を使うことがあります。
水の中で暮らす昆虫もいる
昆虫の多くは森・草原・砂漠などの陸地で暮らしていますが、中には水中で生きる昆虫もいます。たとえば、ゲンゴロウ、タガメなどは水の中で暮らす水生昆虫です。トンボやカゲロウ、ゲンジボタルなど、幼虫のときには水の中で過ごし、成虫になると陸生になる昆虫もいます。
飛ぶ昆虫と飛ばない昆虫
昆虫の中には翅(はね)を持たず飛ばない昆虫もいます。たとえば、アリには翅がなく歩いて移動しますが、生物学的な分類は昆虫です。また、バッタやコオロギは種によって、飛ぶものと飛ばないものがあります。
幼虫と成虫の姿が異なる「完全変態」をする
幼中と成虫の姿が異なる昆虫もよく見られます。幼虫の間は土の中や水の中で暮らし、さなぎを経て成虫になるのです。これを完全変態といいます。カブトムシやチョウは、完全変態の昆虫です。
一方、さなぎを経ずに幼虫からそのまま成虫になる不完全変態の昆虫もいます。カメムシやバッタは不完全変態の昆虫です。
身の回りでよく見かける昆虫
昆虫採集をするときや、普段生活している中でよく見かける昆虫の例を挙げておきましょう。
カブトムシ
クワガタ
カマキリ
バッタ
ハチ
てんとうむし
カナブン
チョウ
トンボ
アリ
ハエ
蚊
身近で見かける昆虫ではない虫
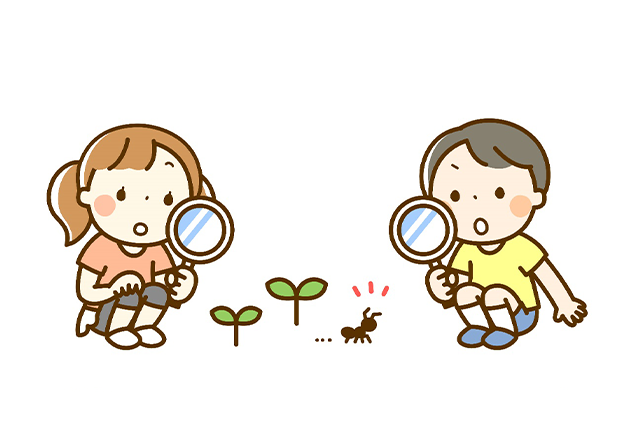
次に、昆虫以外の虫について説明します。
クモ
クモは昆虫と間違えられやすい生き物ですが、脚が8本あるため昆虫ではありません。また、頭部と胸部の区別がないのも昆虫とは異なる点です。
ミミズ
ミミズも普段よく見かける虫といえます。ミミズが多いと土の健康度が高い証明となるため、農業では益虫とされています。
ムカデ・ゲジゲジ・ヤスデ・ゴキブリなど
ムカデ・ゲジゲジ・ヤスデ・ゴキブリなども虫と呼ばれます。害虫のため、駆除の対象となります。
虫か昆虫か迷ったときは体の裏側を確認してみる
虫の種類はとても多く、世界にはまだ発見されていない虫もいると考えられています。一目見ただけでは、昆虫なのかどうか、なかなか区別がつかないこともあるかもしれません。
そのようなときは、つかまえた虫をひっくり返して体の裏側を確認してみましょう。裏側を見ると、体が頭・胸・腹の3つに分かれているかがわかります。合わせて、脚は6本か、翅があるかなど、昆虫の3つの条件を確認してみるとよいでしょう。
また、虫を写真に撮ったり持ち帰ったりして、図鑑や本、インターネットなどで調べるのもよい方法です。
学研教室の会員なら「学研教室ライブラリー」という電子図鑑を利用して、昆虫かどうかを調べることができます。自分で採集した虫を調べてみたいときには、学研教室の「学研教室ライブラリー」をぜひ利用してみてください。





