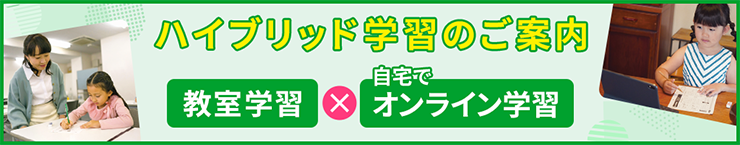2023年9月30日
- 小学生
- 教育
- 学習方法
「デジタルを使った勉強」「紙を使った勉強」の違いとは?特徴を知って効果的に学習を進めるには
最近は、ICT機器を用いた勉強と、紙を使って読み書きをする勉強を選べるようになってきました。それぞれのよさを取り入れて、効果的に学習を進めてることは可能なのでしょうか。紙を使った勉強とデジタルを使った勉強の特徴について解説していきます。
急速に普及したデジタルを使った勉強と、従来の紙を使った勉強

勉強方法には、パソコンやスマートフォンなどのデジタルデバイスを活用した方法と、本やノートなどの紙を使った従来の方法があります。
ICT技術の急速な進歩やGIGAスクール構想、さらに2020年度から始まった新しい学習指導要領で小学校からプログラミング教育が導入され、デジタルを活用した勉強方法はより広く普及するようになりました。
一方で、紙を使った従来の勉強方法にもよさがあり、両方を効果的に用いることで、勉強をより進めやすくなる可能性があります。
子どもが効率的に学習を進めるには、それぞれの特徴をよく知っておくことが大切です。
デジタルを使った勉強と紙を使った勉強について、そのメリットとデメリットをご紹介していきましょう。
「デジタルを使った勉強」のメリットとデメリット

デジタルを使った勉強のメリット
勉強に取り組みやすい
デジタルの教材は、アニメーションを使ってわかりやすくなっていたり、ゲーム感覚で学習に取り組んだりできるものが多く、勉強へのハードルが低くなる工夫がされています。
「勉強しなければ」と構えることなく、気軽に取り組めるのがデジタルを使った勉強のよいところといえます。
視覚や聴覚が刺激される
動画を見たり音を聞いたりすることで視覚や聴覚が刺激され、感覚的に学ぶことができます。小学校で導入されている英語学習やプログラミング学習などは、特にデジタルを使った勉強と相性がよいといえるでしょう。
わからないことがあったときすぐに調べられる
言葉の意味などがわからなかったとき、インターネットを使ってすぐに調べられるのもよいところです。調べ学習をする場合などは、効率的に学習を進めることができます。
間違えやすい問題をくり返し解くことができる
デジタル教材によっては、間違えやすい問題を抽出して、くり返し出題してくれる機能がついていることもあります。苦手な単元がすぐにわかるとともに、くり返し解くことでより学習内容が定着しやすくなります。
勉強した結果をデータ化できる
自動採点や学習履歴などで、勉強した結果をデータ化しやすいのもデジタルを使った勉強の特徴です。子ども自身はもちろん、保護者も子どもの学習状況を把握しやすくなります。
デジタルを使った勉強のデメリット
充電切れなどで端末機器が使えなくなることがある
デジタルの端末機器を使うには、電源や充電が必要です。バッテリーが切れると、端末機器が使えず勉強ができなくなってしまいます。機械が故障してしまった場合やインターネットの接続環境が不安定な場合も、同じく学習できなくなります。
ゲームで遊んだり学習と関係ない動画を見たりする
ゲーム感覚で学べるのがデジタルを使った勉強のよいところですが、ゲームで遊ぶだけになってしまったり、調べものをしているうちに勉強と関係ないサイトや動画を見てしまったりするケースもあります。
視力が下がったり姿勢が悪くなったりする
デジタル機器を長時間見ていると、ドライアイになりやすい、視力が低下しやすいという問題が指摘されています。(*1)また、ブルーライトによる睡眠への影響や、うつむいてスマートフォンを見ることによって姿勢が悪くなることなどから、体に不調が出ることもあります。
(*1) 柴田 隆史.「近視 学校でのICT活用の現状と近視予防」.国立研究開発法人科学技術振興機構.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpnjvissci/40/4/40_40.79/_html/-char/ja
(参照 2023-10-26)
通信容量や通信費がかかる
デジタルを使った勉強をする際には、インターネット環境が整っている必要があります。環境によっては、通信容量や通信費が予想以上にかかるケースもあります。
「紙を使った勉強」のメリットとデメリット

紙を使った勉強のメリット
脳と手を同時に動かすことで記憶に残りやすい
字を書いたり図を描いたりと、実際に自分の手を動かして学習すると記憶に残りやすくなるといわれています。脳と手が協調して働くため、より記憶が定着しやすくなるのです。
たくさんの教材がある
紙の教材は昔から利用されていることもあり、実に多くの種類があります。書店では子どもの年齢や理解度に合わせて、さまざまな教材が販売されており、実際に手に取って内容や教材の雰囲気を確認することができます。子どもの好みや学習の傾向に合わせたものを、自由に選べるのは紙の教材のよさといえるでしょう。
重要なページをすぐに開ける
付せんなどを活用すると、重要なページをすぐに開くことができます。検索窓に検索ワードを入力するといったひと手間がなく、手元にある教材からすぐに目的のページを見つけられるのもよいところです。
色分けなどをして自分なりに使いやすくできる
マーカーなどで色分けして、自分なりに教材を使いやすくすることができます。自分の手で作り上げた教材には愛着が湧きやすく、勉強へのモチベーションアップにもつながります。
紙を使った勉強のデメリット
勉強に取り組むハードルが上がる
気軽に勉強を始めやすいデジタル教材に比べると、鉛筆や教科書などを用意する紙の勉強は、どうしても「勉強しなければ」という雰囲気が強くなります。勉強に対して「難しい」「おもしろくない」というイメージを持っていると、なかなか勉強を始めようという気持ちにならないでしょう。
文字を書くことを負担に感じるケースがある
字を書くことに苦手意識がある子どもには、紙に文字を書いたり消しゴムで消したりすることが負担になるケースがあります。また、低学年で文字を書くことに慣れていないと、時間がかかって勉強するのが面倒になってしまうことがあります。
持ち運ぶ荷物が多くなる
科目によって教科書やノートを分ける必要があるため、荷物が多くなるのもデメリットです。体の小さな子どもにとって、たくさんの教材を持ち運ぶことは負担になるでしょう。
メモを書き込むとすぐ修正できない
紙に書き込んだ内容が違っているときや追加したいことがあったとき、すぐ修正することができません。
鉛筆で書いた場合は消しゴムを使って書き直すのに手間がかかります。また、ペンを使った場合は消すことができず、棒線で消したり修正テープを使ったりしてかえって見にくくなることもあります。
デジタルを使った勉強はより楽しく、紙を使った勉強はじっくり理解を深めるのに向いている
デジタルを使った勉強は、勉強のきっかけ作りや、音やアニメーションなどで楽しみながら学習を進めたいときなどに向いているといえます。
一方、紙を使った勉強は、時間をかけてじっくり理解を深めるのに向いています。
デジタルを使った勉強で効率的に学習を進め、間違いを見つけてしっかり理解を深めていくときに紙を使うなど、工夫をしながら勉強を進めていくとよいでしょう。
また、デジタルの方がよい・紙の方がよいなど、子どもによって好みや適性もあるものです。子どもに合った学習方法を探しながら、効果的な学習方法を見つけられるとよいでしょう。
デジタルを活用した学習方法の一つとして、オンライン学習も一つの選択肢となります。学研教室のハイブリッド学習なら、通室とオンライン学習を組み合わせることで、学習の効率を高めることができます。また、宿題教材は「Google Classroom」を利用して毎日提出できるため、学習習慣の定着にもつながります。デジタルを活用しながら、継続的に学びを深められるハイブリッド学習をぜひご活用ください。