2025年3月26日
- 小学生
- 子育て
- 教育
- 発達
アメリカ発「SEL(ソーシャル・エモーショナル・ラーニング)」で子どもの非認知能力を高める
アメリカでの取り組みが進んでいるSEL教育(ソーシャル・エモーショナル・ラーニング)。SELは、日本でも少しずつ注目を集めるようになってきています。SELとはどのようなものなのか、また、SELを行うことで期待できる効果などについてまとめます。
非認知能力を高めるための、社会性と情動の教育「SEL」
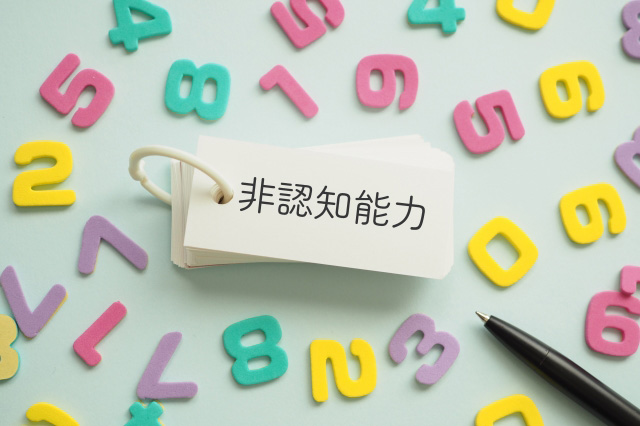
SELとは
SELとは「Social Emotional Learning」の頭文字をとったことばで、日本語では「社会性と情動の教育」と訳されています。知識や技能などの「認知能力」に対して、やる気、協調性、興味や関心、感情などの「非認知能力」を高めていこうという教育です。脳科学や心理学などをベースにして、アメリカを中心にカナダ・イギリスなどで取り入れるところが増えてきています。
なぜ今SELなのか
科学技術の発展やグローバリズムの広がりで世の中が大きく変化するなか、今までのような知識詰め込み型の教育では柔軟に対応できないという問題が、かねてより指摘されてきました。これからの社会を生きる子どもたちには、知識だけではなく、積み重ねた知識を生かす力が必要と考えられます。そのような力を身につけていくため、SELが注目されているのです。
SELの5つの要素
SELでは、次の5つの要素を身につけることを目標にしています。
・自分を理解する力
自分の気持ちや考え方、価値観などを、自分自身で理解することです。自分への理解が深まると、自己肯定感が高まり、自信を持ってものごとに取り組むことができるようになるでしょう。
・自分を管理する力
自分の感情をコントロールして冷静に判断し、自分を管理する力です。ストレスをうまくかわしたり、主体的に行動したりするうえでも、自己管理の力が必要になります。
・社会的な認識
他者や異文化などを理解し、相手の立場に立って広い視野でものごとを考えられる力です。
・良好な対人関係
人の話をしっかり聞き、お互いに協力し合って良好な対人関係を築く力です。コミュニケーション能力と言い換えることもできるでしょう。
・責任のある意思決定
自分が行動したことの結果を予測して、責任を持って判断することのできる力です。
SELを学ぶことで期待できるさまざまな効果

SELの手法を用いて学ぶとどのような効果が期待できるのか、解説していきましょう。
問題解決能力が高まる
子どもが自分自身を知り、しっかり自己管理ができるようになると、先々を見越して適切な判断ができるようになるため、問題解決能力が高まります。学習もスムーズに進みやすくなり、成績にもよい影響が現れます。
自分の気持ちをコントロールできる
SELには、感情をコントロールするスキルが身につく効果があるといわれています。ストレスや不安、怒りなどに対処できると、気持ちが落ち着いて何ごとにも積極的に挑戦してみようと思うようになるでしょう。また、失敗してもすぐに気持ちを切り替えて、再チャレンジしてみようと考えられるようになります。
社会性が向上する
自分の気持ちだけではなく、他の人の気持ちを想像することができるようになり、社会性が向上します。他者と協力しながら建設的にものごとを進められるようになり、責任を持ってさまざまな判断をしていくことができるでしょう。
コミュニケーション能力が高まる
相手の状況や気持ちを思いやりながら人と接することができるようになり、上手にコミュニケーションがとれるようになります。対人関係を良好に保つことは、豊かな人生を送るうえでとても大切なことといえます。また、自分の気持ちを正しく相手に伝えられると誤解が生じにくくなり、お互いの信頼関係も高まるでしょう。
授業の中で行われるSELの具体例

学校では、年齢に合わせたプログラムでSELが行われます。紙芝居や人形劇、ゲーム、身体活動、ロールプレイング、作文を書くなど、さまざまな形式で子どもの非認知能力を高める教育が行われているのです。実際の具体例について、ご紹介していきましょう。
自分のことを模造紙などにまとめて自己理解を深める
クラス全員が輪になってそれぞれの顔が見えるように座ります。お互いに家族のことや好きなこと、将来の夢などについて質問し合い、それぞれ答えていきます。自分で答えた内容をもとに、最後に自分で自分のことを模造紙などにまとめます。質問するときには、相手への敬意を忘れない、嘘はつかないなどのルールを決めておきましょう。他の人のことを知る、自分自身のことをことばにして相手に伝えるという作業の中で、他の人への気づきや自己理解が進みます。
信号の色と感情を結びつける
赤・黄色・青の信号機を紙などで作ります(ライトにカラーフィルムなどを貼ってより本格的に作成することもあります)。赤は強い怒りや恐怖、黄色は不安、青は落ち着いている状態を表します。どのような行動や状態がそれぞれの色に当てはまるかをクラスで話し合い、信号のそばに記入していきます。たとえば赤なら「壁を殴る」「大声で悪口を言う」、黄色なら「おなかが痛くなる」「泣きそうになる」、青なら「安心して落ち着いていられる」「ニコニコしている」などと書いていきます。感情を視覚化することで、気持ちを客観的に理解する訓練になります。
イメージを膨らませながら呼吸をする
深呼吸をして気持ちを落ち着かせる方法です。軽く目を閉じて、大きく呼吸をします。息を吸うときには「焼きたてパンの香りを吸い込む」、また、息を吐くときには「ケーキのろうそくをふーっと吹き消す」など、心地よい状況をイメージしながら呼吸をします。瞑想に似た効果があり、ストレスの回避に役立ちます。
非認知能力の向上は、子どもの将来に役立つ
SELは、アメリカを中心に取り入れられている教育方法ですが、今後日本でも広がっていくことが予想されます。自己理解や感情のコントロール、他者への思いやりを育んでいくことは、子どもの将来に必ず役立つからです。ご家庭でも、子どもと積極的にコミュニケーションをとりながら、非認知能力を伸ばしていけるとよいでしょう。
学研教室では、いち早く非認知能力の向上に着目し、お子さまの健やかな成長をサポートしています。学習教室をお考えの際は、信頼と実績の学研教室をぜひお選びください。





